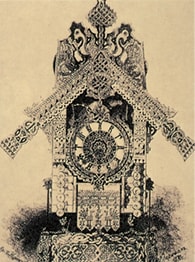|
国民楽派の名曲 今回は「国民楽派の名曲」と題し、チェコのベトジフ・スメタナ(1824~1884)、アントニーン・ドヴォルザーク(1841~1904)、ロシアのピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840~1893)、モデスト・ムソルグスキー(1839~1881)の作品をご紹介します。19世紀のヨーロッパでは、現在まで存続する諸国がそれぞれ「民族意識」を自覚し、独立国家の建設を押し進め始めました。音楽の世界においても、そのような政治的、社会的流れに呼応するかのように、それまでの音楽史においては「辺境」としか扱われていなかった国・地域から、独自の個性をもつ作曲家たちが続々と名乗りを挙げるようになったのです。 ベトジフ・スメタナスメタナ:交響詩《モルダウ》
スメタナの肖像画
スメタナはチェコの「国民楽派」の代表的な作曲家で、自国の歴史や風物などを題材にした作品を数多く残しています。この交響詩は、他の5曲の交響詩とともに、《我が祖国》という連作交響詩を構成する一曲です。《モルダウ》とはチェコを流れる河の名前(チェコ語名は「ヴルタヴァ」)で、愛国心を込めて作曲された《我が祖国》のなかに取り入れるには相応しい題材と言えるでしょう。《我が祖国》の6曲の交響詩は別々に初演されましたが、《モルダウ》は1875年4月4日に初演されています。ほかの5曲が好評を得たのとは対照的に、《モルダウ》の評判はあまり芳しくなかったと言われています。現在では、チェコの「第2の国歌」とも言えるほどに高い人気を誇っていることを考えれば、初演時に好評を得られなかったのはたいへん不思議です。
ドヴォルザーク:交響曲第9番ホ短調作品95《新世界より》
《新世界より》の初演ポスター
アントニーン・ドヴォルザークは、スメタナよりも1世代若い作曲家で、やはりチェコの「国民楽派」を代表する作曲家です。彼の作品のなかで、最も有名なものが、交響曲第9番《新世界より》です。この作品はドヴォルザークの最後の交響曲で、1893年にアメリカで作曲されました(当時、彼はニューヨークのナショナル音楽院の院長を務めていました)。12月16日、ニューヨーク・フィルハーモニックの演奏会で行われた初演は大成功を収め、ドヴォルザークの代表作という評価は現在まで変わることはありません。《新世界より》という標題は、当然ながらアメリカ合衆国のことを表していますが、作曲者自身は「新世界からの印象と挨拶」を表しているだけであると述べています。実際のところ、この作品の根底には、円熟期にあった晩年のドヴォルザークの円熟した筆致があると言ったほうが良いのではないでしょうか。
グリンカ:オペラ《ルスランとリュドミラ》序曲
グリンカの肖像画
ミハイル・グリンカは「ロシア国民楽派の父」と呼ばれています。19世紀初頭までのロシアではフランスやイタリアの影響が強かったのですが、グリンカの世代になってロシア人の音楽家が独自の道を歩み始めたのです。その重要な手段が、ロシア語によるオペラの創作でした。18世紀においてもロシア語オペラは書かれなかったわけではありませんが、外国語オペラを制して、ロシア語オペラの確立に貢献したのがグリンカでした。《ルスランとリュドミラ》は、《イヴァン・スサーニン》(1836年初演)とともに、イタリアとフランスのオペラ様式の影響を受けつつも、ロシア独自の語法を打ちだそうと試みたという意味で、ロシア音楽史上、画期的なオペラと言えるでしょう。
チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調Op.64
この交響曲は1888年に作曲されています。この交響曲の創作の背景には深刻な体験がありました。前年の夏、病に倒れた友人を見舞った時から、チャイコフスキーは死の問題について深く考えるようになりました。実際、当時の作曲メモにはこの交響曲のコンセプトとして次のような書き込みがあるのです。「交響曲の第1楽章の標題。序奏。宿命の前での、あるいは、同じことではあるが、神の摂理の不可解な定めの前での諦念」この書き込みにある「宿命」「神の摂理の不可解な定め」とは、「死」を指すのは明らかでしょう。このような標題的な要素が、この交響曲においてどのように表現されているのかは必ずしも明確ではありませんが、先のノートにあるように、第1楽章冒頭で提示される主題が「宿命」すなわち「死」と関連していると考えても、おそらく間違いないでしょう。
交響曲第5番が書かれたフロロスコエにあるチャイコフスキーの記念碑 第1楽章は序奏を伴うソナタ形式で書かれています。序奏は、既に触れたように「宿命」を表す主題がまずクラリネットで提示されます。この主題は、いわば作品全体のモットーとも言うべきもので、後続の3楽章すべてで顔を出すこととなります(ドヴォルザークの交響曲《新世界より》と同様な手法です)。主部は、まさに「諦念」の情に満ちた、つぶやくような主要主題で始まります。軽快な第2主題の部分では明るい表情に変わるが、暗い情念を晴らすには至らず、この楽章は力無く閉じられます。 第2楽章は、儚い人生への憧れを表すかのように、叙情的な旋律に満たされています。短い序奏の後、ホルンによる主要主題、オーボエで始まる副次主題はどちらもチャイコフスキーの生み出した最も美しい旋律に数えられるでしょう。中間部はややテンポを速め、憂いを含んだ主題がクラリネットに現れます。この部分が徐々に興奮してゆくと、例のモットー主題が力強く奏され、主部へと導きます。この再現では、途中で再びモットー主題が突如として現れて流れをせき止めますが、これは冷酷な「宿命」の存在を表しているかのようです。 第3楽章は「ワルツ」と題されている3部形式楽章です。主要主題も明るい表情のなかに陰りを宿らせていて、社交界の花としてのワルツの姿はもはや感じられません。コーダではモットー主題が長調に変えられて顔を出すが、その表情は、「ワルツ」によって象徴される現世の栄華を儚いものとして力無く否定しているようにも聞こえてきます。 第4楽章は序奏をもったソナタ形式。序奏は、長調に変えられたモットー主題がほとんどそのままで提示されます。しかし、第2、3楽章とは異なってその性格からは「宿命」のもつ厳しさが消えて、宗教的な雰囲気さえ感じられます。この変容は、先に引用した作曲ノートに続いて書かれた「信仰の抱擁に身を任せる」という言葉を連想させずにはいられないでしょう。主部に至って再び「宿命」の厳しさが復活しますが、コーダでは「宿命」に打ち勝った「信仰の抱擁」が勝利の凱旋を果たすかのごとくモットーが力強く現れるのです。 モデスト・ムソルグスキー ムソルグスキー:組曲《展覧会の絵》
《展覧会の絵》の基になった ガルトマンの原画
ムソルグスキーはチャイコフスキーとほぼ同世代の作曲家です。しかし、チャイコフスキーが音楽学校で専門的な教育を受け、職業的な音楽家として活動したのとは対照的に、彼は役所勤めなどをしながら、作曲を続けました。そのために、荒削りな作曲技術が非難されたこともありましたが、その分、既成の手法にこだわらない大胆な筆致を持っているのではないでしょうか。ピアノ独奏のための組曲《展覧会の絵》は1874年に作曲されています。この作品は、作曲者の友人で、建築家・画家として知られていたガルトマンの遺作展での印象に基づいています。
後期ロマン派の名曲(2) (责任编辑:) |